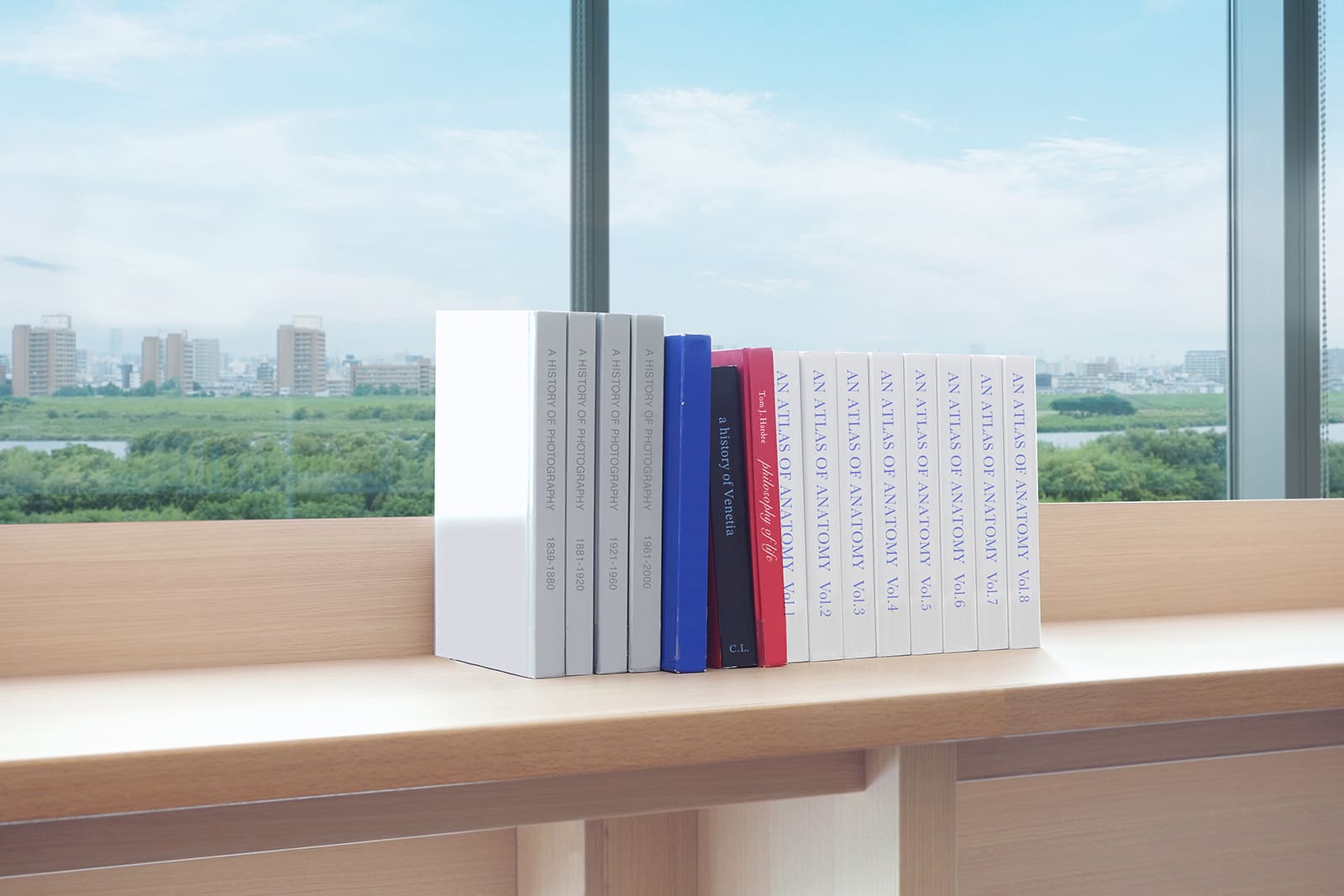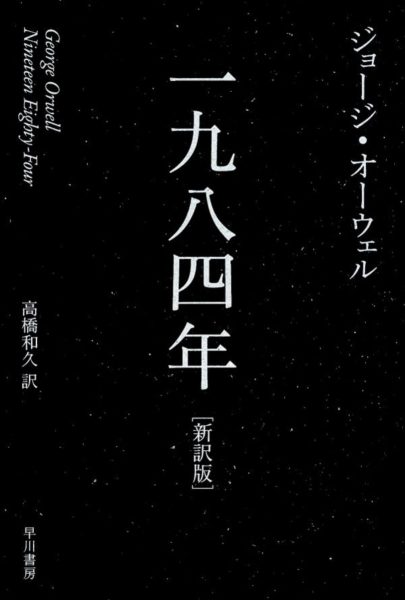
一九八四年(新訳版)
総合人間学系教室大塚 生子 先生推薦
4月―大学ではまた、新しい1年が始まります。
「新しい出会い」「新しい生活」「新しい自分」「夢」「希望」「飛躍」「前進」―そんなポジティブなことばがたくさん浮かびますね。
そんな素敵な季節の折りも折り、今回私は読後感が決して良いとはいえないジョージ・オーウェル『一九八四年』をおすすめします。
『一九八四年』は1940年台末に書かれた、その名のとおり1984年のロンドンを舞台にしたディストピア(ユートピアの反対)SF小説です。世界54カ国の著名な作家100人の投票で決められた「史上最高の文学100」などにも選出され、現在でも思想や文学などの分野に大きな影響を与えている近代文学の傑作のひとつだといわれています。
本書は一言でいうと、「ビッグブラザー」というトップを擁する党によって民衆が管理・支配される社会のお話です。街や職場、家庭内のいたるところに「テレスクリーン」と呼ばれる双方向テレビジョンやマイクが仕込まれ、市民の言動は常に監視されています。ビッグブラザーは絶対的存在であり、党が「今日から2+2=5だ」と言えばそれが「真実」とされ、歴史までもが改ざんされます。そんな社会では、天気予報は決してはずれません。簡単なことです。天気予報が外れて今日雨が降ったら、昨日の記録をすべて「雨だと予報した」ことにすれば良いのだから。
このような社会では、民衆に疑問を抱かせないことが肝要です。党がいうことを無条件に信じる人間を作るためには、何が必要だと思いますか?
この社会では「ニュースピーク」(新語法)が適用されます。たとえば「good」に対して「bad」という表現は不要で、「ungood」で表現できるし、強意も「plus-」や「doubleplus-」という接頭辞をつけて、「非常に良い」なら「plusgood」、「最高に良い」なら「doubleplusgood」と表現できる―このように、語彙の数がどんどん減らされ、人々は反政府的な思想を書き起こす方法を失うのです。人間はことばを通してしか思考できません。ことばを失うことは、思考できなくなることと同義です。
そして、現代の我々にもおそろしく既視感のあるのが、自分で思考しなくなり、党の「正義」を絶対的に信じるようになった人間による、違反者への非難、密告です。体制に疑問を抱き始めた主人公はそんな社会をどのように生きるのでしょうか。
現在の先進諸国には、そんな見えやすい「絶対的権力者」はいません。ですが、「何が正しいか」「どう感じる『べき』か」という、従うべき見えない集団圧力が存在し、違反すると自らを「正義」の代行者と考える輩からバッシングを受け、下手をすると社会的に抹殺される。それを恐れて今度は我々自身がいつの間にかその「正義」に異議を唱えることをやめ、従うことを覚える−これこそ、相互監視社会や無思考の横行といえるでしょう。オーウェルの描いたSFの世界は、もしかしたらそれとわからない形でフィクションではなくなっているのかもしれません。
「2+2=5」には「そんなわけないだろう」と笑えるみなさんですが、大学の「えらい教授」が言ったことにも同じように反発できますか?あるいは「権威ある」ニュースには?新学期は本当に、みんなのいうような「希望に満ちあふれた新しいスタート」ですか?
思考することばを持ちましょう。「当たり前」を疑いましょう。そのために、本をたくさん読みましょう。それができることこそが、主人公ウィンストン・スミスが願った自由な社会なのです。
※図書館報『ぱぴろにくす』117号にご寄稿いただきました。
請求記号・資料ID
- 大宮本館
- 933.7||O 91211892
- 梅田分館
- 933.7||O 97210475
- 枚方分館
- 080||H 98130210