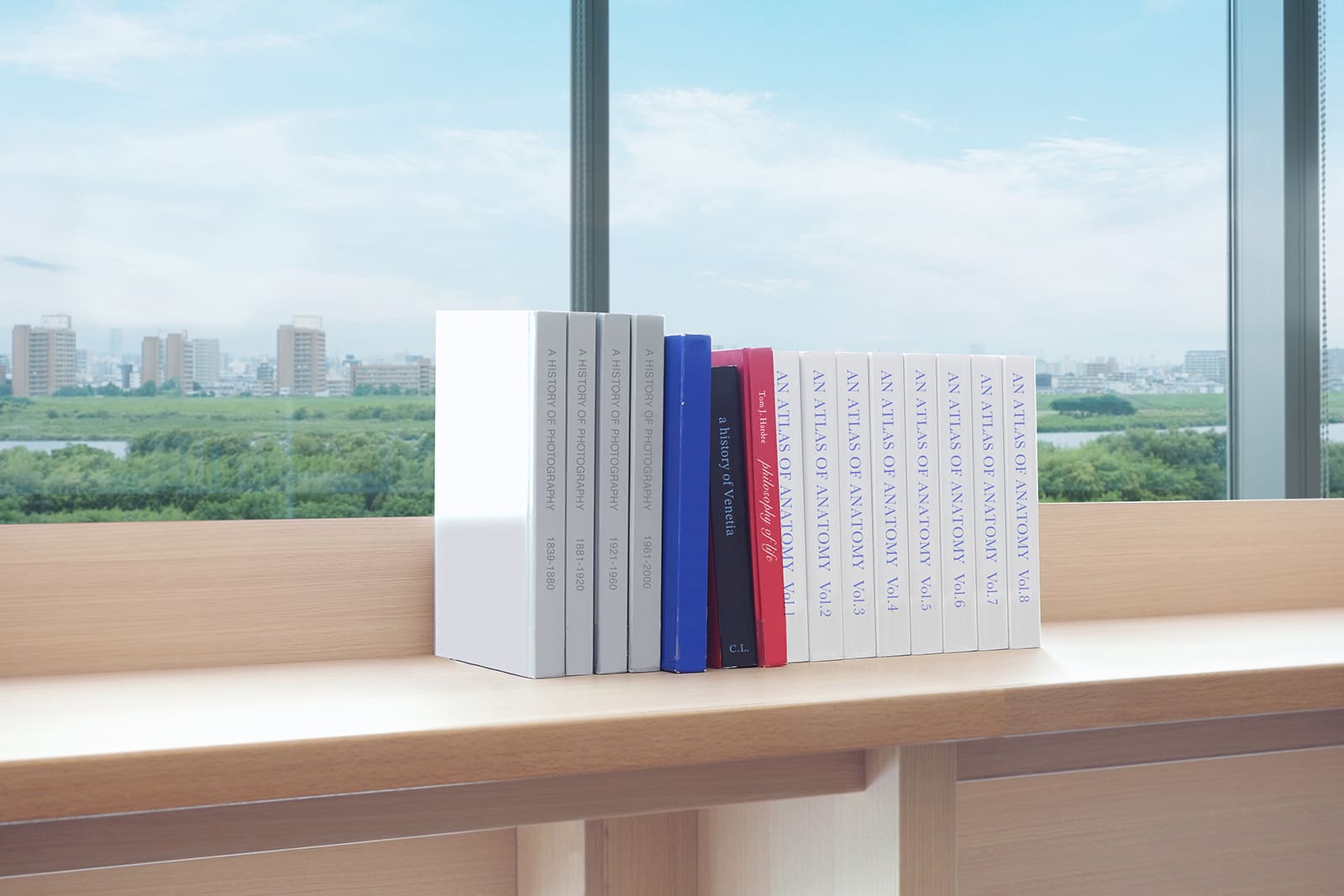-451x600.jpg)
電気工学ハンドブック(第7版)
工学部 電気電子システム工学科見市 知昭 先生推薦
ぱぴろにくすは図書館が好きな人が読まれていると思います。私も図書館が好きです。ただ実は本はあまり読みません。読み始めると夢中になるので、それを抑制しているというのが原因のような気がします。すみません、只の言い訳です。さて、そんな私が何の本を薦めるのかというと〇〇ハンドブックという図書になります。ハンドブックとは便覧のような必要な事項を簡潔に説明した参考図書の一種という意味がありますが、百科事典と変わらない巨大なものもあり、今回は後者のものとなります。電気系の分野であれば、電気工学ハンドブックというものがあり、他の分野でも各種ハンドブックが存在しています。
私が最初にハンドブックと出会ったのは、大学院修士課程の頃です。自分の研究で用いている放電プラズマがどういうものなのかを調べるために、大学図書館に籠り、高電圧・放電工学の専門書を読み漁っていました。この手の専門書は数多くあるものの、調べたい内容が書かれていない、説明の内容が本ごとに微妙に異なっているなどといった具合で、何が正解なのかもわからなくなるという事態に陥りました。そんな時、偶然見つけたのが放電ハンドブックでした(一般的にハンドブックは専門書コーナー以外のところに置かれています)。
手に取ったハンドブックは20数年前の当時では新書籍でした。多くの専門家が集まって、十分な議論をしたうえで執筆していったのでしょう。専門書ではカットされていた内容がこれでもかと書かれていて、夢中になってページをめくった記憶が今でも残っています。また体系的にまとめられているので、全体を把握する際に有効です。ただ、結局自分の研究で用いている放電プラズマが何に分類されるのかはよくわからなかったのですが。それでも内容が面白かったので何度も図書館に通って読んでいました(禁帯出だったので)。
放電ハンドブックは残念ながら1998年発行となっており、その後も改訂版は出ていませんので、特に本学科の学生には電気工学ハンドブック(第7版)をお薦めしたいと思います。謳い文句がまた凄くて、「電気工学分野の金字塔」です。放電ハンドブックほどマニアックではないですが、幅広い電気工学分野を細分化して、それぞれを詳しく説明しています(全47編です)。電池や家電の話なども専門書よりも詳しく書いている部分があるので、手元にある教科書では物足りない人は手に取ってみてはいかがでしょうか。数式以外の部分も多く読み物としても優れていると思います。情報社会で何でもネットで入手できる時代となりましたが、百科事典並みの膨大な情報ともなると手元で見た方が快適ですよね。他の学科の学生さんも自身の分野にあったハンドブックを探してみてください。専門分野の理解がより深まると思います。
請求記号・資料ID
- 大宮本館
-
540.36||D 11301060
540.36||D 11301654 - 梅田分館
- 540.36||D 71607071
- 枚方分館
- R540.36||D 82400005