情報メディア学科
- トップページ
- 情報メディア学科

情報メディア学科インスタグラム
FM802の番組「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-」とのコラボレーション企画を実施
FM802の番組「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-」で、本学との特別コーナー企画「Seeds For The Future」が放送されました。 情報メディア学科の学生がラジオ収録に挑戦し、大学の魅力やプロジェクト活動、研究活動について発信しました。 ニュース、 大阪工業大学×ROCK KIDS 802 特設サイト|
|
|
|
情報メディア学科で目指す、あなたの未来

情報メディア学科では、単に情報システムを設計開発する知識の習得だけではなく、使いやすく、直感的にわかりやすい、言葉、画像、音、体感を駆使した表現力の高い情報システムを開発できる人材を育成します。
取得可能な資格の例
基本・応用情報技術者
CGエンジニア検定ベーシック・エキスパート
ウェブデザイン技能士
卒業後の進路
本学科卒業生の過去3年間(2020~2022年度)における就職先の一部を紹介します。多くの卒業生はシステムエンジニアとして様々な分野のシステム開発に関わっています。
また、情報メディア学科では、より深い知識や技術習得のため、大学院へ進学する学生が多いのも特徴であり、大学院修了後は情報メディア分野の専門知識を活かした職に就くことも多いです。(参考:大学院修了後の就職先(他学科卒の大学院生の就職先も含む))
主な就職先 (2020年度-2022年度)
ソフトウェア・情報処理・通信
インターネットイニシアティブ、SGシステム、NECソリューションイノベータ、NECネッツエスアイ、NTTデータSMS、オージス総研、オプテージ、関電システムズ、京セラコミュニケーションシステム、さくらケーシーエス、GMOインターネット、システナ、Sky、T&D情報システム、DTS、ドコモ・システムズ、トヨタシステムズ、日立システムズ、日立社会情報サービス、富士通Japan、三菱電機インフォメーションネットワーク、三菱電機ソフトウエア、明治安田システム・テクノロジーほか
電気・電子系メーカー
イシダ、Dynabook、富士通フロンテック
自動車関連メーカー
スズキ
電気・通信・設備等工事業
NTTフィールドテクノ、ミライト・ワン
各種卸売・小売業
大塚商会
金融業
近畿産業信用組合
その他
大和ハウス工業、TBSアクト、日本総合研究所、パナソニックシステムソリューションズジャパン、三菱電機エンジニアリングほか
過去の就職率についてはこちらをご覧ください。
卒業生インタビュー
 |
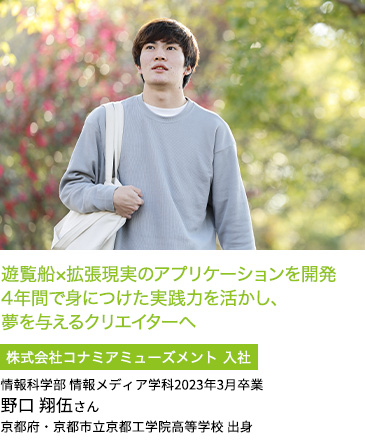 |
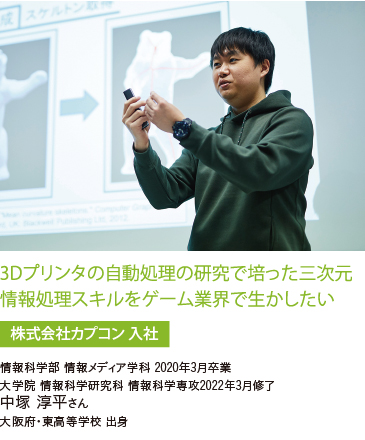 |
 |
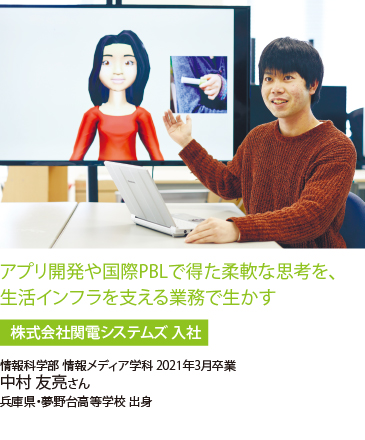 |
情報メディア学科で学ぶ、体験する、身につける
授業:各種メディアに対する情報処理技術を学び、それらを駆使したシステムを構築
情報メディア学科では、 プログラミング技術に加え、3次元画像処理、音声・音響処理、言語処理、パターン認識、ヒューマンインタフェースといった様々な メディアに関する情報処理技術を学びます。 その後、演習科目や学生プロジェクト、卒業研究等において、こうした 技術を応用したシステムの開発を行い、 実践的な技術の習得を目指します。
情報メディア学科で学んだことの集大成として、3年後期に実施される情報メディア演習IIIでは実際に社会に役立つコンテンツを制作する演習を行っています。
ひとつは人とCGエージェントが楽しく対話するシステム、もうひとつはマルチメディアデータ編集技術を駆使して、川上村を世界にPRする動画コンテンツです。
以下には過去の学生達が制作したコンテンツを紹介します。
情報メディア演習Ⅲ「人とCGエージェントが楽しく対話するシステム」
画像処理による顔認識や音声合成・認識ソフトウエア(MMDAgent)を用いて,人とCGエージェントが楽しく対話するシステムを構築します。
※MMDAgentは名古屋工業大学で開発されたオープンソフトウエアです。
以下は受講者が作成した「目指せ高得点~ひらめきと学びの冒険~」のプロモーション動画です。ぜひご覧ください(音が出ますのでご注意ください)。
 Copyright 2009 Nagoya Institute of Technology (MMDAgent Model "Mei")
Copyright 2009 Nagoya Institute of Technology (MMDAgent Model "Mei")
 Copyright 2009 Nagoya Institute of Technology (MMDAgent Model "Mei")
Copyright 2009 Nagoya Institute of Technology (MMDAgent Model "Mei")
情報メディア演習Ⅲ「奈良県川上村を世界にPRする動画コンテンツ」
奈良県川上村と連携し、マルチメディアデータ編集技術を駆使して、川上村を世界にPRする動画コンテンツを制作します。
優秀作品は川上村から表彰されるとともに、下記川上村のWebページで一般公開されます。
ー令和5年度の優秀作品ー
金賞:KAWAKAMI TRIP 冨田 暁翔 さん
銀賞:川上の大自然 林 愛子 さん
銀賞:Kawakami 三宅 志門 さん
こんなコンテンツの制作能力がつくカリキュラム内容は ここをクリック!
その他の魅力的な学び
情報メディア学科では皆さんの技術・能力を向上させる数多くの講義・演習が用意されています。そのなかの一部を下記に紹介します。
- プログラミングの学習
-
1年次には、未経験者も含めてプログラミング技術の基礎をしっかりと身に付けます(プログラミング入門:1年前期、C演習I:1年後期)。2年次以降は、より高度な内容へと発展させ、ゲーム・ソフトウェア・システム開発に必要な技術を学習します。(C演習II:2年前期、Java演習:2年後期、ソフトウェア工学演習:3年前期)

- 音楽・CGを使ったオリジナルアニメーションの制作
-
ミュージック・シーケンサとシンセサイザによる音楽制作法や、3次元CGアニメーション生成ソフトの操作を習得し、音楽とアニメを統合して自分のオリジナル作品を仕上げます。(アニメーション演習:1年前期)

- 情報メディア技術の基盤となるマルチメディアデータ
-
マルチメディアを構成する画像・音声・映像などのディジタルデータの 特性や処理、圧縮に関する理論・アルゴリズムを学習します。(メディアデータ論:1年後期)

- ウェルカムビデオの作成
-
自分が所属する学部や学科を紹介する「ウェルカムビデオ」を作成しています。監督やシナリオライター、音響監督、デザイナーなどのロールプレイを通じ、グループで3分間に凝縮したビデオ作品を完成させます。(情報メディア入門:1年後期)
2023年度最優秀作品:ウェルカムビデオ
- コンピュータグラフィックス制作技術を身に付ける
-
コンピューターグラフィックス(CG)と画像処理の基礎知識を学ぶとともに、CGソフトを使った演習を通じて、CG制作の基礎技術を習得します。(コンピュータグラフィックスⅠ:2年前期)

- 身近な「音」の仕組みをさぐる
-
音声や音楽など、「音」は身近にあふれています。人はどうやって音を聞くのか、なぜ音階は「ドレミファソラシド」なのか。音にまつわる幅広い話題について、その仕組みや実用例を学びます。(音響処理:2年前期)

- 情報システムと向き合う人間の情報学
-
モーションキャプチャを用いた人間の身体動作の測定や、視線追跡装置を用いた人間の視線行動の分析を行うことにより、人間行動を情報として捉え、情報システムと向き合う人間の知覚や挙動への理解を深めます。(人間情報学:2年前期)

- 映像処理・画像認識によるシステム開発
-
映像処理や機械学習による画像認識のプログラミングを学習し、カメラ映像を用いたインタラクティブなシステムやゲームを開発します。(情報メディア演習II:3年前期)

- Androidスマートフォンアプリの開発
-
PythonによるプログラミングやHTMLとCSSによるWEBデザインを学習し、自由な発想で対話エージェント等オリジナルのAndroidスマートフォン用アプリを開発します。(情報メディア演習II:3年前期)

- 現実世界とコンピュータグラフィックスの融合
-
2次元画像/映像処理・3次元コンピュータグラフィックスの高度な技術および、現実世界とコンピュータグラフィックスの融合である、拡張現実・複合現実・バーチャルリアリティについて学びます。また、実際にプログラムを動かし理解を深めます。(コンピュータグラフィックスⅡ:3年後期)

- 卒業研究
-
4年次に研究室に配属され卒業研究を行います。指導教員の指導の下、4年次末には研究成果を卒業論文にまとめ、卒論発表会で発表します。完成度の高い研究は学会などで対外発表する機会もあります。卒業研究を通して、実践的なメディア処理についてのスキルや考え方を身につけます。

キーテクノロジー:世界の最先端を行く、AI、XR、メディア情報処理技術の数々
ビッグデータ解析や人工知能、機械学習等、様々な メディア情報処理技術を用い、 便利で楽しく、豊かな世界の実現を目指して、日々研究を行っています。
- 自律移動ロボットの製作
-
様々なセンサから得られる情報に基づき人間の生活を支援するロボットを開発しています。ハードウェアも設計・製作しています (センサ情報処理研究室)
- 仮想空間で異文化体験
-
アメリカの文化を疑似体験しながら「かぐや姫」のストーリーに沿って、宝探しゲームをする仮想空間を開発しました。VR酔いを軽減する移動方法として、足による移動、ワープ移動、ウィンクや瞬きなどのアイジェスチャによる移動を実装しています。( ヒューマンインタフェース研究室)

- 不可能を体験できるVR 防災トレーニング
-
現実にできない火災体験やその中での避難訓練、消火活動を体験できるインタラクティブなVRコンテンツを開発しています。火災や避難の状態は、実際の火災での避難モデルを元に再現し、現実に近い形で防災訓練を行うことが可能です。(インタラクションデザイン研究室)

- 感情豊かにロボットと対話
-
人間同士のコミュニケーションでは,相手の気持ちや感情を考えながら対話をしますよね。同じようにロボットも相手の気持ちを推測できれば,より自然な対話を実現できます。DNNやLSTMといった人工知能の方法を用いた,高精度な感情推定を研究しています。(音声・音楽情報処理研究室)

- VRにおける移動感覚・触れる感覚
-
実際には移動していないのにあたかも移動しているような臨場感を表現する方法や、触れていないのにあたかも触っているような触力覚を提示する方法について研究しています。(感覚メディア研究室)

- 画像・映像マジックとXRへの応用
-
あるはずの物がカメラ映像に映らない?無いはずの物がカメラ映像には現れる?まるでマジックを見せるかのようなカメラ画像・映像の処理技術を研究開発しています。また、そのような技術をXR(AR・MR・DR・SR・VR)に応用する研究を行っています。(視覚情報処理研究室)

- 試験問題を解く人工知能の研究
-
最新のディープラーニングや自然言語処理技術により試験問題を解く人工知能の開発を行っています。共同参加しているNIIの「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトでは、全国88%の私立大学で合格可能性80%を達成する人工知能が実現されています。(自然言語処理研究室)

- 3Dプリンタでデザインを現実に
-
3Dプリンタの登場でデザインを現実のものにすることが可能になりました。パーツへの分解や組み立てやすさの考慮など、より自由に、より効率的に出力する方法について研究しています。(Visual Computing 研究室)

- VR疑似体験により生活習慣改善・認知力向上
-
仮想の生活空間を構築し、行動履歴を分析し、片づけなどの生活習慣を改善したり認知能力を向上させるトレーニングシステムを開発しています。ゲームの要素を取り入れるなどの工夫をしています。( インタラクションデザイン研究室)

- 人間らしい振舞いをするエージェントやロボットの開発
-
対話エージェントや人型ロボットが、対面での接客や受付役として活躍する期待と需要が高まっています。人間らしさや親しみを感じる対話を実現するためには、それらに人間がとるような自然な振舞いや感情表現をさせる必要があります。当研究室では、人間らしいうなずき、視線、表情、ジェスチャ、姿勢などをとるエージェントやロボットを開発しています。( ヒューマンインタフェース研究室)

- あなたの楽器演奏を自動評価
-
楽器演奏の練習をしていると、「よい音でてるかな?」「テンポは 大丈夫かな」と心配になりますね。そんなあなたに、 音の高さや長さ、音量、音色等、様々な項目をチェックし、 「上手な演奏」ができるよう、システムが自動でアドバイスしてくれます。( 音声・音楽情報処理研究室)

- モーションARでアーチェリー練習を支援
-
人間のモーションをセンサで捉え、それにコンテンツを重ね合わせるモーションAR(拡張現実感)の研究を行っています。具体的には、アーチェリーのトレーニングを支援するシステム(動作例)を開発しています。( インタラクションデザイン研究室)

- プロテウス効果を仮想空間上で体験
-
仮想空間で魅力的な外見のアバタを使用すると、実際の自分より外向的になり積極的な行動をとるようになることが知られており、「プロテウス効果」と呼ばれています。当研究室では、このプロテウス効果を、仮想空間でのデート、オンライン会議、筋トレシステム等に応用し効果を実証しています。( ヒューマンインタフェース研究室)

- 複合現実感によるコンテンツをプログラミング
-
現実世界と仮想世界を融合した空間の中で、ジェスチャや音声などのメディアを介して、通常では起こりえないことを疑似体験できるコンテンツやシステムを開発しています。これにより、新しい世界が広がります。( インタラクションデザイン研究室)

学生プロジェクト:答えのない課題をチームで解決
現実世界の様々な課題に対して、学生が主体となって解決策を検討し、システムを構築します。チームで活動することで、問題解決能力に加え、 コミュニケーション能力の向上を目指します。
- 画像処理・CGを用いた地域課題解決
-
産官学が連携・協力し、健康、街づくり、防災などの地域課題をAIデータサイエンス的アプローチにより解決を目指す学生プロジェクトを実施しています。情報メディア学科所属の学生チームは、情報科学部が立地している大阪府枚方市の観光活性化を目指し、観光船の位置情報を利用した「大阪の歴史」や「水辺の魅力」を学べるアプリケーション、現存しない百済寺をCGとして復元し画像に合成する拡張現実感(AR)システムなどの開発を行いました。
枚方市主催のイベントで活用された様子
「水都大阪」未来の体験型水辺観光
- 異文化メディアコンテンツを海外の大学と共同で制作
-
異なる文化を持つ国の学生同士がチームを組み、与えられた社会的課題を解決しうるメディアコンテンツを共同で制作するワークショップを毎年実施しています。昨年度は韓国芸術総合学校(K-Arts)、北海道大学、済州漢拏大学、東北芸術工科大学と連携し、「水」を題材としたプロジェクトに取り組みました。

- VRを使ったホームロボットシミュレーションの開発
-
家庭でサポートしてくれるロボットのシミュレーションの開発をしています。このシミュレーションはVRを使うことで、人とロボットとの様々なコミュニケーションの課題にチャレンジすることができます。このような家庭内でのサポートするロボットの競技会であるロボカップやWRSに、シミュレーションリーグが発足した2018年から参加し、準優勝3回、3位入賞1回、敢闘賞1回を受賞しています。(プロジェクトのページ)

- 社会的課題をゲーム的に解決するアプリ
-
安心安全、少子化、育児、ゴミ処理など身近な社会的課題を、ゲームの要素やメディア技術を取り入れ、解決するアプリをグループで企画・開発しています。成果は、公の場で発表し、頂いたコメントを開発にフィードバックし、よりいいものをつくっています。

- 仮想ミュージアムコンテンツを制作
-
国立民族学博物館における食文化展示で、拡張現実感技術や高臨場感技術などの情報メディア技術を活用し、仮想たこ焼き体験、仮想包丁さばき体験、食感シミュレータ体験など8つの作品を展示しました。
韓日食博 ―わかちあい・おもてなしのかたち
- 屋外を自律走行するロボットの開発
-
自動運転の基本技術を検証するために屋外用の自律走行ロボットを開発しています。将来的には屋外のゴミを回収するロボットの実現を目指し、自律走行だけでなく画像処理による物体認識などの機能なども搭載しています。公道でロボットを自律走行させる競技会である中之島ロボットチャレンジに2021年度から参加しています。ロボットが動いている様子はこちら(動画1、動画2、動画3)です。

- ゲームクリエイトプロジェクト(GCP)
-
ゲームクリエイトプロジェクト(GCP)は、個人やチームでゲーム制作を行います。ゲームを制作するために、PDCAサイクルを何度も繰り返し、「考える、やりきる、振り返る」力を身につけ、ゲームを完成させることで「ユーザに遊んでもらいフィードバックを得る」経験をすることができます。ユーザを楽しませるためのゲーム制作を通じて、「人を知ること」「わかりやすく魅力を伝えること」など、社会に出ても使える実践的なスキルを身につけることができます。
(プロジェクトのページ)

